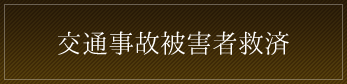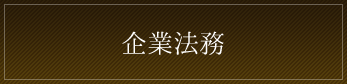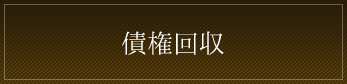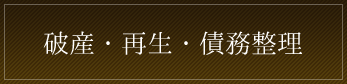相続財産の帰趨(預貯金債権を除く)
Aさんが死亡すると,Aさんを被相続人とする相続が開始され(民法882条),遺言による遺産分割方法の指定が無ければ,相続財産ごとに帰属先が変わります。
可分債権・債務
賃料債権,借入金債務といった財産は,判例上,当然分割対象財産として指定相続分又は法定相続分にしたがって各相続人に帰属します。つまり,相続人間での共有とはならず,遺産分割手続が不要です。
もっとも,遺産分割手続において,相続人の合意を得られれば,遺産分割対象財産として取り扱うことも可能です。
祭祀財産
系譜,祭具(仏壇・位牌・遺影),墳墓,遺骨等の祭祀財産は,相続承継の対象とならず,①被相続人の指定,②慣習,③家庭裁判所の指定(審判手続)の順で別途承継先が定められます(民法897条1項・2項)。
その他の財産
当然分割対象財産・祭祀財産以外の相続財産は,相続人間での共有となります(民法898条)。そして,遺産分割の協議・調停・審判が確定すれば,相続開始時に遡及して遺産分割内容にそった相続人に帰属します。
相続債務の注意点
相続債務の帰属先について,遺産分割手続で法定相続分以外の割合で相続人に帰属した場合でも,あくまでもその効力は相続人間でしか通用しません。したがって,債権者からは,法定相続分での債務負担を求められても拒否することはできないのです。