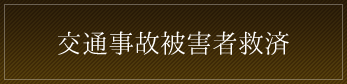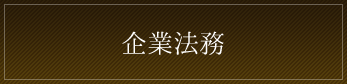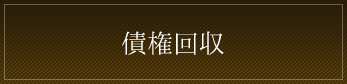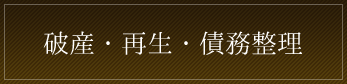遺言能力
Q1 認知症の方は遺言を作成できるのか?
Q2 成年被後見人の方は遺言を作成できるのか?
Q3 字が書けない方は遺言を作成することができるのか?
Q4 口・耳・目の不自由な方は遺言を作成することができるのか?
遺言能力
遺言能力とは,単独で有効に遺言を行うことができる資格です。遺言書が成立要件を満たしていても,相続人や遺言執行者によって被相続人に遺言能力がなかったとの反論が認められれば,当該遺言は無効です。
遺言能力は,以下の2点が要件となります。
①遺言時に15歳以上であること(民法961条)
②遺言時に遺言内容及びこれに基づく法的効果を弁識・判断する能力があること(解釈)
よく争いになるのは上記②であり,裁判例を見ると,被相続人が軽度(長谷川式)の認知症であり,かつ,遺言内容が複雑ではない事案では,遺言能力を肯定していますので,“認知症=遺言能力なし”とは言えません。もっとも,認知症の方が遺言書を作成する場合には,リスクヘッジの方法としては,遺言の種類を公正証書遺言にして公証人による本人状況等録取書添付,医師の診断書添付,遺言作成過程をビデオ撮影して保管,といったことが考えられます。
行為能力制限は適用されない
ある人が法律行為を行っても,行為能力に制限(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人)があれば,事後的に取消しが認められてしまいます。しかし,遺言作成の場面では,行為能力制限規定の適用が廃除されており(民法962条),上記遺言能力があれば原則として遺言書作成が可能です。
もっとも,成年被後見人は,通常は事理弁識能力を欠いているため,遺言能力を有しない蓋然性があることから,当該能力が一時回復した場合であっても遺言書作成時には医師2名以上の立会及び事理弁識能力を有することの付記・署名・押印が追加成立要件として課されます(民法973条)。
自署・自書ができなくても遺言可能
遺言の種類が自筆証書遺言の場合には,遺言者本人による全文自書及び署名押印が成立要件であるため,字が書けない方は作成困難です。
そこで利用したいのが公正証書遺言となります。全文は公証人が録取した上で遺言者に確認すれば良く,自署能力が無い場合には公証人がその事由を付記することで代用できます(民法969条4号但書)。
口・耳・目が不自由な方でも遺言可能
公正証書遺言は,公証人が,❶遺言者から遺言趣旨の「口授」並びに遺言内容の「口述」を受けて録取し,❷その内容を遺言者に「読み聞かせ」ることが必要です。平成11年の民法改正により,口のきけない方の場合には❶について「通訳人の通訳による申述」又は「自書」に代用できるようになり,耳の聞こえない方の場合には❷について「閲覧」に代用できるようになっています。