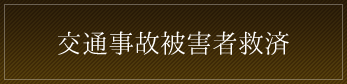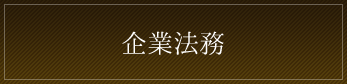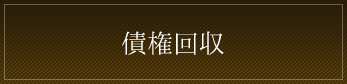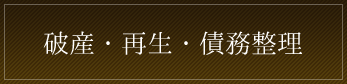遺留分とは
遺留分とは,相続財産中,法律上その取得が一定の相続人に留保されていて,被相続人による自由な処分(贈与・遺贈・相続分指定)に対して制限が加えられている持分的利益です。
遺留分算定の基礎財産
各相続人の個別的遺留分額を算出するには,まず基礎財産を確定する必要があります。相続財産≠基礎財産であることがポイントです。基礎財産は,「被相続人が相続開始時に有した財産」に一定範囲の「生前贈与した財産」を加え,最後に「相続債務」を除去した残額です。
「被相続人が相続開始時に有した財産」
・相続財産中の積極財産
・遺贈又は相続させる旨の遺言の対象とされる財産
・死因贈与の対象とされる財産
一定範囲の「生前贈与した財産」
・相続開始前1年以内に贈与された財産
・贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを承知でした贈与の財産
・生計の資本として贈与された財産〔特別受益〕
「相続債務」
・主債務者が無資力時の保証債務
※遺言執行費用・相続財産管理費用・相続税・葬儀費用は含まれない。
遺留分割合と個別的遺留分額
相続人に直系尊属以外が存在する場合,基礎財産に乗じる総体的遺留分率は2分の1であり,個別的遺留分率は各人の法定相続分と同じです。
したがって,大多数の場合,①基礎財産に法定相続分の半分の割合を乗じた金額に,②自らが受け取った上記一定範囲の「生前贈与した財産」を控除した金額が,あなたの個別的遺留分額になります。
遺留分侵害額の算定
ここまでくれば,あともう一歩。具体的な遺留分侵害額は,あなたの個別的遺留分額から,Ⓐ未処理の相続財産に相続分を乗じて自らが取得しうる金額を控除し,Ⓑ自己の相続債務分担額を加算して算出します。
相続債務分担額は,遺言書記載の指定相続分(指定が無ければ法定相続分)で乗じて特定しますが,包括遺贈や相続財産全部の相続させる旨の遺言の場合には,当該受遺者に全ての相続債務負担が生じることから他の相続人に相続財務分担額はないとするのが判例です。