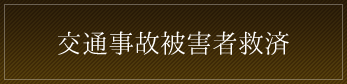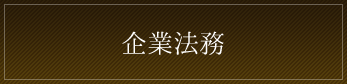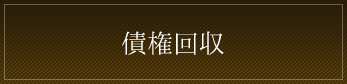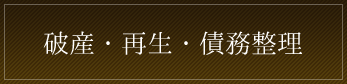特別受益
遺産分割協議を行なう場合、亡くなられた人の名前で現在残っている財産(遺産)だけが対象となるものではありません。
生前に、相続人の一人に対して、ある程度まとまった財産が与えられているときは、特別受益として、いったん現在残っている財産に持ち戻して、遺産の範囲を確定させ、その分け方を協議することになります。
したがって、特別受益として認定されるかどうかは、遺産分割の際、大きな影響があります。
特別受益として認定されない形で、生前に財産を取得している場合、その人は有利となると言っても良いと思います。
特別受益として認定されないテクニックがあるのか?
ここからが、「不思議な裁判所の認定シリーズ」の始まりです。
父親(被相続人)が会社を経営していて、息子ないし娘の一人(相続人)が会社から給料、退職金を取得していた場合、特別受益としての認定はむつかしくなります。法人格(会社)が介在することによって、裁判官は、特別受益の認定を容易にはしなくなるのが現実です。
このような現実を踏まえ、相続が発生するより随分前に、特別受益として認定とされないよう工夫することが必要なのです。