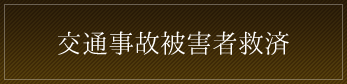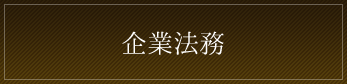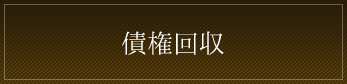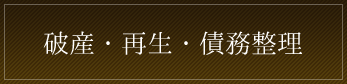任意後見契約
本人の判断能力低下前に、本人と任意後見人の予定者とが任意後見契約を締結します。この契約締結の時に、本人が委任事項を含む任意後見契約の内容を理解していることが必要です。
この契約には、任意後見監督人が家庭裁判所により選任されたときから契約の効力が生ずる旨の特約が付けられます。
任意後見契約は、公正証書により締結される必要があります。また、公正証書が作成されると公証人は法務局へ登記を嘱託し、任意後見契約の登記がなされます。この登記は、プライバシーに関わる事項であり、登記事項証明書の交付を請求できる者は限定されています。
本人の判断能力が不十分になった場合、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立をします。
家庭裁判所は、本人の判断能力が不十分と認めるとき、任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力を発生させることになります。