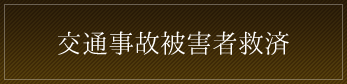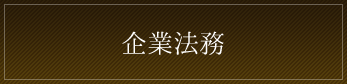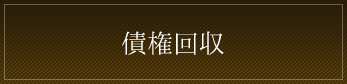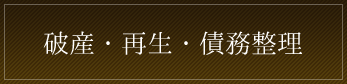民法改正による商法改正(1)
民法大改正
民法(債権関係)の大改正が行われます。施行期日は、一部を除いて、平成32年4月1日と決まりました。この民法改正に伴い、実は、商法や会社法も改正されています。「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下では「整備法」という。)により、商法や会社法も改正されるのです。そのうち、数回を使って、民法改正に伴う商法改正のお話をしたいと考えます。
民事法定利率の改正と商事法定利率の廃止
まず、民事法定利率に関する規定が改正されます。
現在は、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」(民法404条)という内容です。
これが、「法定利率は、3%とする。」(新民法404条2項)となります。
なお、これは、3年に一度見直すという変動制です(新民法404条3項・4項)。
これを受けて、商法514条の商事法定利率に関する規定が廃止されます(整備法3条)。
「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。」(商法514条)という条文が廃止されるのです。
その結果、商行為によって生じた債務に関しても、新民法404条2項が適用され、3%となります。6%から3%への変更はきわめて大きな変更です。
商取引では、通常は、利息が生じる場合には、契約書において、約定利率が定められますので、多くの場合には、民法419条適用による遅延損害金に適用されます。これまでは、現在の様々な利回りからは考えられないような6%が適用されてきましたが、平成32年4月1日からは、3%となります。
したがいまして、遅延損害金につきましても、約定利率をきちんと定めて、取引を行うように心がけたいものです。